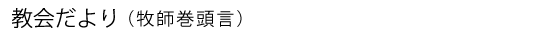No.40 2011年10月9日
弱さに働く神の恵み
牧師 石田 透
人間はだれでも弱さを抱えて生きています。弱さの質は様々で、そのことを重荷に感じて日々あえぎながら生きている人もあれば、時に弱さをあらわにしながらも、そのことには全く無自覚で日常を生きている人もいます。聖書は人間の「弱さ」をどう見ているのでしょうか。
また「病む」ということはつらいことです。使徒パウロにも持病がありました。「てんかん」とも、抑うつ的な精神疾患とも言われていますが、想像の域を出ません。彼はそれを「肉体のとげ」と表現しています。「とげ」はそのまま訳せば「先のとがった棒のようなもの」です。柔らかな肉体にはとても受容できないような代物です。まさに異物です。それが彼に与えられたのです。パウロはそれに苦しみながらも、それを深く受容しているというのです。
弱さと自覚される病気との付き合いの中で、パウロは神の恵みの何たるかを知り、弱さをついに受け入れていきました。しかしそれは決して平坦な道のりではありませんでした。その苦しみは「涙の手紙」と言われる第二コリントの10~13に詳しく描かれています。
パウロは苦しみつつも、深く豊かなかけがえのない経験をしていきます。「苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったことも度々でした。」(IIコリント11・23)それがパウロの経験したことです。その厳しい経験をくぐり抜けてパウロはこう告白します。「誇る必要があるなら、わたしの弱さに関わる事柄を誇りましょう。」(11・30)その経験をパウロはコリントの教会の人々に熱心に語るのです。しかしなかなか心は通じ合えませんでした。
もともとコリントの教会の人々は貧しく無力な群れでした。イエスの十字架の死という無力さの極みの中に神の愛が現れるということを、最も正しく受けとめられるはずの人々でした。しかし現実はどうだったのでしょうか。福音の受け皿として最もふさわしい彼らでありましたが、その弱さは逆の方向に作用してしまいました。その弱さが霊的熱狂主義に転じてしまうというのがコリントの教会の人々の問題でした。
パウロは主イエスの十字架へと今一度帰っていく中で、自分の無力さの自覚を促されていきました。病が「与えられている」という表現は、普通の感覚からはなかなか出て来ない表現です。それはまさに信仰告白です。私たちの経験の世界ではマイナス符合のつく「弱さ」が、イエスさまの十字架の死を通して示された出来事(福音)においては、その同じ「弱さ」が「恵み」となるというのが、神の側での「真理」なのです。「弱さに働く恵み」とは、逆説ではなく、まさに人を生かす真理なのです。福音とはそのようなものです。
私たちも「弱さ」や「欠け」を人間的な尺度からではなく、また強がりでもなく、大きな神の視点からまさに自分を発見し、人と人とを繋ぐ、神の恵みとして受けとめていきたいと思います。